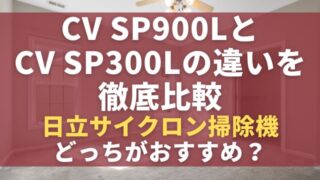桜の花言葉は怖い?「私を忘れないで」という言葉の秘められた意味

春はお花見の季節です。
お花見に行かれる方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、お花見にちなんで、桜の花言葉に関するテーマでをお伝えいたします。
桜はバラ科の植物で600以上の種類があります。
日本の野生種にはヤマザクラやオオヤマザクラ、オオシマザクラなど約10種が含まれます。
これらは栽培品種として多くの選抜が行われ、ソメイヨシノもその一つです。
それぞれの品種には特有の花言葉がありますので、できるだけ多くのものをお伝えしていきます。
また、花言葉の由来についても調査しましたので、参考にしていただければと思います。
さらに、「桜の花言葉は怖いから、桜にまつわるものを贈るのはやめたほうがいい」といった話を聞いたことはありませんか?
桜の花言葉は、日本で知られているのは「精神の美」「優美な女性」「純潔」です。
これらに恐怖を感じることはありません。
しかし「桜の花言葉は怖い」と感じている、またはそのような話を聞いたことがある、という方も多いようです。
なぜでしょうか。
結論から申し上げますと、これは、根拠のない噂に過ぎません。
「桜の花言葉が怖い」の背景には、文学作品や伝説が影響していて、また桜の花の短い寿命とも関連しています。
春の訪れを象徴し、日本人の心に深く根付いた桜。
その美しさの中には、儚さや「影」も感じられることがあります。
この記事では、桜の花言葉が恐ろしいとされる背景、感動的な物語、さまざまな種類の桜の花言葉について詳しく掘り下げていきます。
桜の花言葉が恐ろしいと言われる5つの理由

桜の花言葉は、日本で知られているのは「精神の美」「優美な女性」「純潔」です。
これらに恐怖を感じることはありません。
「桜の花言葉が怖い」の背景には、文学作品や伝説が影響していて、また桜の花の短い寿命とも関連しています。
ここでは、桜の花言葉が恐ろしいとされる背景、感動的な物語、さまざまな種類の桜の花言葉について詳しく掘り下げていきます。
桜の花言葉に対して恐れを抱く理由は次の通りです。
- フランス語での桜の花言葉「私を忘れないで」の影響
- 梶井基次郎の作品『櫻の樹の下には』の影響
- 木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)の神話からの影響
- 桜の花の短い寿命と儚さの印象
- 武士を象徴する花としての意味
これらの点について、詳しく見ていきましょう。
フランス語での桜の花言葉「私を忘れないで」の影響
フランスにおける桜の花言葉は「Nem’oubliez pas(ヌ・ムビリエ・パ)」で、「私を忘れないで」と訳されます。
この花言葉には2つの由来があります。
- 桜の花が散る様子が寂しく、儚いこと
- 騎士が遠征に出る際に、礼拝堂を桜で飾る伝統があったこと
過去に戦争で恋人たちが離れ離れになることが多かった時代、出征する男性に対し、女性たちは桜の花を飾り、「私を忘れないで」という願いを込めました。
このような背景から「桜=別れの花」というイメージが生まれ、花言葉として定着しました。
この由来を知ると、恐怖ではなく感動的なエピソードとして受け取られることでしょう。
ただし、この花言葉を「重たい」と感じる人もいるかもしれません。
そうした感覚から、桜の花言葉に重さや恐怖を感じるという話が広まったのです。
※ちなみに、フランス語で「忘れないで」という表現は、勿忘草(忘れな草)の名前としても知られています。
梶井基次郎の作品『櫻の樹の下には』の影響

梶井基次郎の短編『櫻の樹の下には』は、桜の木に関する特異な視点を表現しています。
この物語は、桜の木の下に死体が埋まっているという斬新な発想を提示し、桜の美しさがその下にある死体によってもたらされるという考えを展開しています。
この物語は、生と死が密接に結びついており、美しさの背後には恐怖が隠れていることを示唆しています。
「櫻の樹の下には」は、「桜=恐怖」というイメージを強化し、坂口安吾の「桜の森の満開の下」と共に桜の恐ろしい一面を強調しています。
これらの作品の影響で、現代における桜の花言葉に否定的な印象が生じている可能性があります。
木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)の神話からの影響
日本の神話において、コノハナサクヤヒメは桜を象徴する女神です。
彼女にまつわるエピソードが、桜の花言葉に暗い影を投げかけています。
この物語では、美しいコノハナサクヤヒメに求婚する神、瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)が登場します。
彼女の父、オオヤマズミノカミはこの結婚を喜びますが、磐長姫(イワナガヒメ)という彼女の姉も嫁として提案されると、ニニギノミコトは彼女の外見を理由に拒否します。
この出来事により、オオヤマズミノカミは人間の命が花のように儚いと宣言し、神話には悲しく、少し怖い雰囲気が漂います。
桜の花の儚さの印象

桜の花は、その散る様子の儚さで知られています。
この特徴は、美しさと共に不吉な側面としても捉えられてきました。
例えば、江戸時代には桜の家紋の使用を避ける傾向があったり、庭に桜の木を植えることが忌避されることもありました。
その美しさにも関わらず、桜の木は庭木として敬遠されることもあります。
日本人にとって、桜は遠くから鑑賞するものであり、その儚さが桜の花言葉に悪いイメージを与える一因となっているかもしれません。
武士を象徴する花としての意味
歴史的に桜は、武士の生き様を象徴する花とされてきました。
「花は桜木、人は武士」という諺がその証拠です。
桜の儚さは、主君への忠誠を示す武士の命への執着を捨てる姿勢を象徴していました。しかし、この考え方は命を軽んじる姿勢とも解釈され、一般の人々には恐怖として映ることもありました。
桜を見る際、その美しさの中に武士道の激しい側面を感じ取る人もいたため、桜の花言葉に恐怖のイメージが添えられた可能性があります。
すべての桜に通じる花言葉は

桜の花言葉は、「精神の美」「優雅な女性」「純潔」といった概念を象徴しています。
「精神の美」
桜は日本の国花として、国民性や高潔さの象徴とされています。
これは、精神性や自制心、精神的耐久力を意味し、これらの特質は武士道から来ていると言われています。
「優雅な女性」
日本女性の美が称えられています。
歴史的に桜の優雅さと日本女性の美しさが比較されることが多く、桜の小さく整った花びらや色合いが、日本女性の繊細さや強さを表しています。
「純潔」
桜の無垢な美しさからきており、特に花びらが白からピンクへ変わる様子が純粋の象徴とされています。
西洋では、「精神の美」(spiritual beauty)と「優れた教育」(a good education)の花言葉が存在します。
日本でも西洋でも、桜の花言葉は美しさや儚さを連想させます。
これは、桜の満開の美しさや散る時の清らかさから、外見だけでなく内面の美しさや儚さを感じさせるものです。
西洋の花言葉「spiritual beauty」と「a good education」は、ジョージ・ワシントンの子供時代の逸話に基づいています。
若かりしワシントンが父の大切にしていた桜を間違って伐採し、正直に告白したことで誠実さを評価されたとされます。
しかし、その時代にアメリカに桜が存在していなかったという説もあり、その話の真偽は不明です。
桜の品種別花言葉

サクラはバラ科の植物で600以上の種類があります。
日本の野生の桜はヤマザクラ、オオシマザクラ、オオヤマザクラ、タカネザクラ、エドヒガン、マメザクラ、ミヤマザクラ、タカネザクラ、チョウジザクラ、カスミザクラ、クマノザクラの10種、諸説あるカンヒザクラを含めると11種です。
これらは栽培品種として多くの選抜が行われ、ソメイヨシノをはじめ、多くの種類があります。
それぞれの品種には特有の花言葉があり、ここではポピュラーなサクラの花言葉を紹介します。
染井吉野(ソメイヨシノ)のメッセージ
「高貴」「清純」「精神美」「精神愛」「優れた美人」
これらは、ソメイヨシノが示す観賞用桜の代表的な美しさと、その花が散る際の潔さを象徴しています。
ソメイヨシノ特有の清らかで愛らしい美しさや、純粋なイメージを称える花言葉です。
八重桜(ヤエザクラ)のメッセージ
「理知」「しとやか」「豊かな教養」「善良な教育」「理知に富んだ教育 」
旭山桜(一才桜)など、花びらが重層的に重なるヤエザクラには、これらの花言葉が付けられています。
ヤエザクラは、その重なった花びらが洗練された印象を与え、「しとやか」はその控えめな花の姿に由来します。
また、「豊かな教養」と「教育的洞察」は、花の豊かさが教養と知識を象徴しているとされています。
枝垂れ桜(シダレザクラ)のメッセージ
「優美」「純潔」「精神美」「淡泊」「ごまかし」
柔らかく枝を垂れる枝垂れ桜は、これらの特性を持つと言われています。
「ごまかし」は、枝が下に垂れる様子が、まるで真実を隠しているのを象徴していると解釈されます。
「淡泊」は、その清楚で優美な散り際が、物への執着を持たない性質を表しています。
河津桜(カワヅザクラ)のメッセージ
「思いを託します」「純潔」
静岡県賀茂郡河津町に自生する河津桜は、毎年多くの観光客を引き寄せています。
「純潔」は、河津桜の純粋な美しさを象徴していますが、「思いを託します」の起源ははっきりしていません。
山桜(ヤマザクラ)のメッセージ

「あなたに微笑む」「高尚」「美麗」
山間部に自生するヤマザクラは、その自然な美しさで知られています。
奈良県の吉野桜が特に有名で、ソメイヨシノに似ていますが、開花時には葉が同時に現れることが特徴です。
「あなたに微笑む」は、その早春の花が人々に暖かさをもたらす様子から来ています。
大山桜(オオヤマザクラ)のメッセージ
「純潔」「優美さ」
オオヤマザクラは、「純潔」と「優美さ」で知られています。
これらは桜が日本文化において持つ、始まりの象徴や一瞬の美しさ、儚い美を表しています。
深山桜(ミヤマザクラ)のメッセージ
「高潔」「純潔」
主に日本の高山や寒冷地で見られる深山桜(ミヤマザクラ)は、朝鮮半島や中国東北部、サハリンにも生息域を広げています。
この桜の種は、その生育地から「高潔」と「純潔」を象徴する花言葉を持っています。
冬桜(フユザクラ)のメッセージ
「冷静」
冬季に冷たい空の下で咲く冬桜は、その清冽な美しさで「冷静さ」を象徴しています。
冬桜は山桜と豆桜の交配種であり、冬だけでなく春にも花を咲かせることがあります。
これらの季節に静かに花を咲かせる冬桜から、「冷静」というイメージが生まれました。また、この種は小葉桜とも呼ばれることがあります。
江戸彼岸(エドヒガン)のメッセージ

「心の平安」「独立」
江戸彼岸は本州、四国、九州の山間部に自生する天然の桜です。
彼岸の時期に花が開くことから名付けられ、その独立した美しさから「独立」という花言葉も持ちます。
この種は最大で20~30メートルまで成長し、その荘厳な姿から「心の平安」を象徴します。
高嶺桜(タカネザクラ)のメッセージ
「あなたの微笑み」「優美な女性」「潔白」「心の美しさ」
寒冷地に自生する高嶺桜は、適応力が強いことで知られています。
高地で成長するため、しばしば曲がりくねった低い姿勢で育ちます。
開花時期は晩春で、ミネザクラ(峰桜)とも呼ばれることがあります。
大島桜(オオシマザクラ)のメッセージ
「心の美しさ」「純潔」
大島桜は、白い花と香り高い葉で知られ、これらは和菓子に使用されます。
伊豆大島で自生するこの種は、春の初めに緑の新葉とともに美しい白花を咲かせます。
その清楚で繊細な姿から「心の美しさ」「純潔」の花言葉が与えられています。
寒緋桜(カンヒザクラ)のメッセージ
「気まぐれ」「艶やかな美人」「あなたに微笑む」「善行」
寒緋桜は、その鮮やかな緋紅色の花が特徴で、日本の沖縄県や石垣島にある「荒川の寒緋桜自生地」などで見られる亜熱帯性の桜です。
その明るい花色は「魅力的な美人」を連想させ、早咲きの特性から「気まぐれ」とも表現されます。
また、その暖かい気候で育つことから「あなたに微笑む」という花言葉も生まれています。
この桜は日本国内外で見られ、花びらが落ちずに萼が付いて落ちるという独特の特性があります。
寒桜(カンザクラ)のメッセージ

「気まぐれ」「あなたに微笑む」
1月から2月にかけて咲く早咲きの寒桜は、「気まぐれさ」を象徴しています。
この花はしばしばフユザクラと間違えられることがありますが、赤みがかった花を年に一度だけ咲かせることからその名前が付けられました。
特に熱海地方に多く、地元ではアタミザクラ(熱海桜)とも呼ばれています。
霞桜(カスミザクラ)のメッセージ
「希望」「純潔」「高尚」「淡白」「美麗」「あなたに微笑む」
霞桜は大型の落葉高木で、盃型の特徴的な樹形を持っています。
花が散った後には紫黒色の実がなり、その苦味が特徴です。
花言葉に「希望」が含まれるのは、春の訪れとともに咲くその花が新たな始まりと未来への希望を象徴するためです。
この桜は、淡いピンク色の花と春先の開花時期に他の桜と一緒に美しく咲き誇ります。
丁字桜(チョウジザクラ)のメッセージ
「純潔」「高尚」「心の美」「優れた美」「淡泊」「美麗」
丁字桜はその独特な花形から名付けられ、小さく下向きに咲く花が特徴です。
これにより一般的な桜と比べて控えめで洗練された印象を与え、美しさと高貴さを象徴しています。
観賞用としてはあまり一般的ではありませんが、その独特の美しさは高く評価されています。
鬱金桜(ウコンザクラ)のメッセージ
「優れた美人」「心の平安」
黄色い花が特徴の鬱金桜は、別名「美人桜」とも呼ばれています。
この桜は、その特異な黄色い色合いがウコンに似ていることから名付けられました。
時間が経過すると花色が黄色からピンクへと変化するこの桜は、山梨県昇仙峡にある金櫻神社で特に尊ばれています。
ここでは、「金の成る木」として神木に指定され、金運向上の象徴としても親しまれています。
花言葉には「優れた美人」「心の平安」があり、その美しさと心を落ち着かせる効果が評価されています。
豆桜(マメザクラ)のメッセージ

「優れた美人」「淡泊」「純潔」
豆桜は小さな花と低い樹高が特徴で、その控えめながらも魅力的な姿から、この花言葉が付けられています。
富士山や箱根周辺の自然豊かな地域に多く自生しており、その地域特有の名称としてフジザクラやハコネザクラとも呼ばれます。
庭桜(ニワザクラ)のメッセージ
「高尚」「秘密の恋」「うつろいやすい愛」
ニワザクラは、花が開くと中心にある緑の葉が見えなくなることから、秘めた恋や移り気な愛情の花言葉が生まれました。
この桜は寒さと暑さに強く、小さめの樹高で個人の庭でも育てやすい品種として知られています。
紫桜(ムラサキザクラ)のメッセージ
「精神の美」「優美な女性」「純潔」
ムラサキザクラは紫色の花を咲かせる種で、特有の花言葉を持たないため、一般的な桜の花言葉が適用されます。
その豊かな色合いから、精神の美や優美な女性、純潔といった意味が込められています。
熊野桜(クマノザクラ)のメッセージ
「精神の美」「優美な女性」「純潔」
2018年に新しい野生種として発見された背景を持つ熊野桜は、三重県南部から和歌山県南部の山間地に自生する桜です。
新種として発見されたこともあってか、固有の花言葉はありませんでしたので、桜全般に共通する「精神の美」「優美な女性」「純潔」が花言葉と言えます。
この桜は花が咲く前に葉が出ることが特徴で、美しい薄ピンク色の花を春に咲かせます。
里桜(サトザクラ)とは栽培品種の総称のこと
里桜は、オオシマザクラを基にした栽培品種を中心に、多くの野生種との交雑によって誕生したサクラの種間雑種群です。
この群は特に日本のサクラ栽培品種の多様性を示すもので、八重咲きのヤエザクラを含む多数の品種があります。
サクラの国際的な花言葉
サクラは世界中で愛されており、アメリカのワシントンDCのタイダルベイスンやスウェーデンのストックホルム王立公園など、多くの国で桜が観光の魅力となっています。
各国によってサクラの花言葉は異なる意味合いを持ちます。
以下、いくつかの国の代表的な花言葉を紹介します。
英語での花言葉「優れた教育」(eminent instruction)
この花言葉はアメリカ初代大統領ジョージ・ワシントンが幼少期に起こしたエピソードに由来します。
彼が父親の大切にしていたサクラの木を切り倒し、その後すぐに罪を認めて正直に謝罪したことから、このエピソードはアメリカで道徳教育の一環として頻繁に引用されます。
アメリカの桜は、約100年前に日本から贈られた苗木が原点で、毎年ワシントンD.C.のポトマック公園で行われる「全米桜祭り」は、70万人もの訪問者を集める人気のイベントです。
フランス語での花言葉「私を忘れないで」(Nem’oubliez pas)
フランスでは、「私を忘れないで」という花言葉があり、サクラの花の散る寂しさや儚さを象徴します。
これには、遠征に出る騎士が礼拝堂に桜を飾る伝統が関連しており、戦地に赴く男性に対して残された女性が忘れられないよう願いを込めたとされています。
韓国語での花言葉「心の美しさ」(정신의 아름다움)「美人」「佳人」(가인)
韓国では、「心の美しさ」「美人」「佳人」という花言葉があり、これは日本の「優美な女性」と類似した意味合いを持ちます。
これらは花の美しさや、存在感の清潔さを直接的に表現しています。
韓国の桜は過去に日本軍によって植えられたものが多いですが、1960年代に済州島原産の王桜と認められ、桜への愛着が深まりました。
現在、4月の花見の時期にはソウルの汝矣島公園で大規模な花祭りが行われています。
花言葉の起源と意義

花言葉の起源はトルコに遡り、「セラム」と呼ばれる「花に想いを託して恋人に贈る」風習がヨーロッパに伝わり、そこから花言葉としての文化が日本にも伝えられました。
ヨーロッパでは特に貴族間で恋愛の駆け引きに花言葉が使われることがあります。
現代では、花言葉はギフトを選ぶ際の参考にされることが多く、特に誕生日や母の日などのイベントでその植物の特徴や背景を表現する手段として利用されています。
花言葉の決定方法は?
花言葉は特定の決まりがなく、誰かが提案したものが広まり定着することが多いです。
また、花言葉は「宣伝文句」や「販売戦略」としても利用されることがあります。
新しい種類の花が開発された際には、その花の開発者や販売者が花言葉を創出することも一般的です。
花言葉の起源
花言葉が割り当てられる際には、通常何らかの由来が存在します
。逸話や象徴的なイメージに基づいて、花に特定のメッセージが付与され、その花が表す意味が形成されます。
神話や伝説からの花言葉
ヨーロッパでは、ギリシャ神話やその他の伝説に登場する花に花言葉がつけられることが多いです。
例えば、アネモネの「はかない恋」は、ギリシャ神話でアフロディテが愛したアドニスの死に際して咲いた花から来ています。
水仙の「うぬぼれ」は、自分の映像に魅入られたナルシスの話に由来しています。
花の特性に基づく花言葉
花の外見や特性からインスピレーションを受けて花言葉が生まれることもあります。
パンジーの「物思い」は、花がうつむく姿から連想されますし、カモミールの「苦難に耐える」は、その丈夫さから来ています。
椿の「謙虚」は、美しい花形に反して香りがないことから付けられました。
色による花言葉の変化
同じ種類の花でも、その色によって花言葉は異なります。
赤い花は「情熱」や「熱愛」と関連づけられ、ピンクの花はより優しい愛の表現とされます。
白は「純真」や「清潔」を象徴し、黄色は「嫉妬」や「裏切り」といったネガティブな意味合いを持つことが多いです。
これらの色によるイメージは、花を贈る際に考慮する重要な要素です。
桜の種類ごとの花言葉と「怖い」印象の理由まとめ
桜全体には「精神の美」と「優れた美人(優雅な女性)」という花言葉がありますが、各品種にはそれぞれ独自の花言葉が存在します。以下に各品種の花言葉を一覧で紹介します。
| 桜の種類・品種 | 花言葉 |
|---|---|
| 染井吉野(ソメイヨシノ) | 「高貴」「清純」「精神美」「精神愛」「優れた美人」 |
| 八重桜(ヤエザクラ) | 「理知」「しとやか」「豊かな教養」「善良な教育」 「理知に富んだ教育 」 |
| 山桜(ヤマザクラ) | 「あなたに微笑む」「高尚」「美麗」 |
| 枝垂れ桜(シダレザクラ) | 「優美」「純潔」「精神美」「淡泊」「ごまかし」 |
| 河津桜(カワヅザクラ) | 「思いを託します」「純潔」 |
| 大山桜(オオヤマザクラ) | 「純潔」と「優美さ」 |
| 深山桜(ミヤマザクラ) | 「高潔」「純潔」 |
| 冬桜(フユザクラ) | 「冷静」 |
| 江戸彼岸(エドヒガン) | 「心の平安」「独立」 |
| 高嶺桜(タカネザクラ) | 「あなたの微笑み」「優美な女性」「潔白」「心の美しさ」 |
| 大島桜(オオシマザクラ) | 「心の美しさ」「純潔」 |
| 寒緋桜(カンヒザクラ) | 「気まぐれ」「艶やかな美人」「あなたに微笑む」「善行」 |
| 寒桜(カンザクラ) | 「気まぐれ」「あなたに微笑む」 |
| 霞桜(カスミザクラ) | 「希望」「純潔」「高尚」「淡白」「美麗」「あなたに微笑む」 |
| 丁字桜(チョウジザクラ) | 「純潔」「高尚」「心の美」「優れた美」「淡泊」「美麗」 |
| 鬱金桜(ウコンザクラ) | 「優れた美人」「心の平安」 |
| 豆桜(マメザクラ) | 「優れた美人」「淡泊」「純潔」 |
| 庭桜(ニワザクラ) | 「高尚」「秘密の恋」「うつろいやすい愛」 |
| 紫桜(ムラサキザクラ) | なし。「精神の美」「優美な女性」「純潔」 |
| 熊野桜(クマノザクラ) | なし。「精神の美」「優美な女性」「純潔」 |
また、「怖い」と印象がある理由については以下の通りです。
- 桜の花言葉には直接的に怖い意味は含まれていない
- フランスの花言葉「私を忘れないで」とその影響
- 日本神話や小説に由来する影響
- 武士の精神を象徴する花としての儚い姿
- 桜の美しさの背後に潜む「影」による怖いイメージ
桜はチューリップやヒマワリとは異なり、影のある花という印象が強いです。
これらの特徴が様々な説を生み出し、怖さを感じさせる雰囲気につながっています。
これらの要素が組み合わさって、桜に関する現在のイメージが形成されていると考えられます。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。