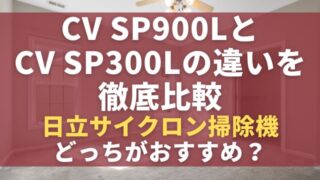コンビニでは買えない退職届の封筒!購入方法や提出までの流れについて
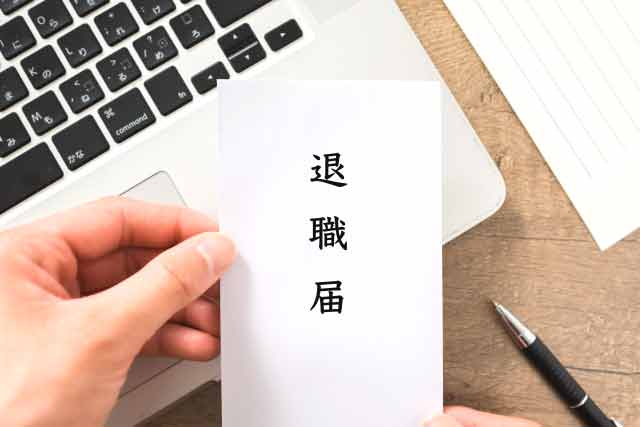
新たな道を進むため退職を決意された方へ、まずは退職届の準備から始めましょう。
退職を申し出る際には「退職届」が必要ですが、適切な封筒を見つけるのは案外難しいかもしれません。
コンビニで退職届用の封筒は取り扱っているでしょうか?
実は、ほとんど扱っていません。Amazonなどのオンラインショップで購入するのが手早く安心です。
100均や文房具店での入手も難しいため、退職が決まったら早めに手配を進めましょう。
この記事では、退職届用の封筒がコンビニや100均で手に入らない理由を解説します。
封筒の選び方や記入方法、送り方についても詳しくご説明しますので、最後までご覧ください。
退職届用封筒はコンビニではなく通販での購入がおすすめ

退職が近づいているなら、退職届と封筒を準備することが大切です。
封筒はコンビニで見つかりにくいため、通販での購入が最も確実です。
本章では、封筒の購入場所や選び方について詳しく解説します。
通販での購入が手早くて安心!余裕をもって注文することがポイント
転職や退職は、キャリアアップや収入向上のために行われることが多いです。
退職を決意したら、職場に退職の意向を伝え、「退職届」とその封筒の準備が必要です。
封筒はコンビニや100均、文房具店ではほとんど取り扱っていません。
近くのコンビニやドラッグストア、スーパー、文房具店で探しましたが、郵便局に問い合わせても見つかりませんでした。
「封筒はどこでも手に入ると思っていたけど、退職届に適したものが見つからないとは…」と思うかもしれません。市販されている封筒でも、退職届用の特定の条件を満たすものはなかなかありません。
封筒の選び方には次のような条件があります。
・郵便番号の枠がなく、無地であること
・白色であること
・中身が透けないように二重構造であること
・封筒のサイズは用紙のサイズに合わせること
適切な封筒を見つけるのは難しいですが、オンラインでの購入が確実です。
例えば、【オキナ】製の白い封筒・長3号・枠なし・17枚入りもオンラインで見つかります。
楽天市場やモノタロウでの取扱いもありますので、通販の利用をおすすめします。商品が届くまでには時間がかかるので、早めの注文が重要です。
封筒の選び方についてさらに詳しく説明します。
白色で無地のものを選ぶのがベスト、長形3号・4号が適切
退職届用の封筒には特定の色やサイズが求められます。
適当に選ぶわけにはいきません。基本的かつ重要なポイントをお伝えします。
基本①白色で無地の封筒
ビジネス用途では、封筒は「白色」と「茶色」が一般的ですが、退職届には「白色」が推奨されます。
特に、外側が白色で内側が見えない紫色の紙で補強された「白封筒」「二重封筒」が適しています。
市販の封筒には郵便番号を印刷しているものもありますが、退職届は通常直接手渡しするため、郵便番号欄は必要ありません。
基本②適切な封筒サイズの選び方
退職届を入れる封筒のサイズは、退職届の用紙サイズに合わせることが重要です。
一般的に退職届の用紙はB5またはA4サイズです。それに合わせて三つ折りに収める封筒サイズを選びます。
・B5(182×257 mm)用は長形4号(90×205 mm)
・A4(210×297 mm)用は長形3号(120×235 mm)
どちらのサイズも選ぶことが可能です。それぞれの特性についても解説します。
B5サイズはコンパクトさが特徴のポケットサイズ
B5サイズの用紙と長形4号の封筒の組み合わせは、コンパクトでスーツの内ポケットや手帳に収まります。
目立たずに渡したい場合は、B5サイズがおすすめです。
A4サイズ・長形3号はスタンダードでアクセスしやすい
A4サイズの用紙と長形3号の封筒は、一般的で家庭でもよく使われます。自宅のPCで退職届を作成できるテンプレートも利用しやすいです。
ただし、三つ折りにした後のサイズはスーツの内ポケットには入りにくく、他人の目に触れる可能性が高いです。
A4サイズは、コンパクトさを重視しない方や自宅での作成を希望する方に適しています。
退職届封筒のエチケット!記入から収納までのマナー詳解

用紙と封筒の選定後は、「書き方」に焦点を当てて詳しく説明します。
封筒の記入方法や退職届を封筒に入れる際のマナーについて詳しく説明します。
3ステップで完了する封筒の記入方法
「マナーが複雑で理解しにくい」と感じるかもしれませんが、「大丈夫です、一つ一つ説明します。」
手順①適切な筆記具の選定
封筒の表面も裏面も「黒色のボールペン」または「万年筆」で記入します。
サインペンや筆ペンは避けましょう。これらは文字を目立たせすぎる恐れがあります。
推奨される筆記具は、「油性インク」を使用した「0.7mm」のペンです。
退職届は重要な文書であるため、インクが消えたり滲んだりしないよう適切な筆記具を使用することが求められます。
0.7mmのペンは適度な太さで、読みやすい文字が書けます。
万一のために予備の封筒も用意しておくと安心です。丁寧な筆跡で記入しましょう。
手順②「退職届」「退職願」の表記方法
封筒の表面上部中央に、「退職届」または「退職願」とはっきりと記載します。宛名の記入は必要ありません。
「退職届」と「退職願」は、見た目は似ていますが、重要な違いがあるので注意が必要です。」
【種類と特徴】
退職届
・退職の事実を正式に通知する文書
・一度提出すると基本的に撤回不可能
・退職の明確な意志がある場合に使用
退職願
・退職の申し出をする文書
・提出後、承認前であれば撤回が可能
・柔軟な退職交渉を望む場合に適用
「もし勤務条件が改善されるなら退職しなくてもいいかも」と考えている場合は、退職願が適しています。
退職願は撤回が可能ですが、時に不利な印象を与えかねないので、提出は慎重に行うべきです。
手順③所属部署と氏名の記入方法
封筒の裏面左下に、所属部署名と自分の氏名を記入します。
これで準備は完了です。次は封筒に入れるだけです。
三つ折りの正しい方法!封はそのままでOK
封筒に入れる前の準備は難しいものではありませんが、正しい折り方と封筒への入れ方が重要です。
手順①退職届(退職願)の三つ折り方法
退職届を作成した後、文面が内側に来るように平らな面で「三つ折り」にします。
三つ折りの手順は以下の通りです。
- 文書の表面を上にして机に置きます。
- 下部の「3分の1」を上に向かって折ります。
- 上部の「3分の1」を下に折り返します。
折り目を正確に合わせ、きれいに仕上げましょう。
【美しく仕上げるコツ】
A4サイズは一辺が99mm、B5サイズは一辺が85mmになるよう折ると美しく仕上がります。定規を使うとさらに正確に折れます。
手順②封筒への入れ方
封筒の「裏面」を上にして、三つ折りした退職届を90度左回りに回転させて入れます。
退職届の右上角が封筒の裏側から見て右上に来るように配置します。
手順③封は通常閉じない
これで完成しました。封はノリで密封する必要はありません。
【注意点】
既にノリ付きの封筒を使用する場合、封をして「〆」マークを中央に記します。
〆マークは封筒が未開封であることを示すためのものです。記入を忘れないようにしましょう。
退職届を手渡しまたは郵送する際のエチケット
退職届を封筒に入れた後は、それをどのように渡すかが重要な段階です。適切なマナーを守りながら、双方が良好な関係を保ちつつ次のステップへと進むことが重要です。
この章では、退職届の適切な渡し方について詳しく説明します。
就業規則を守り、直属の上司に直接渡す
退職届の提出にはタイミングが重要です。
法律で定められている「退職意思の表明は退職する14日前までに」というルールがありますが、できれば1か月前には提出することが望ましいです。
【重要なポイント】
職場の就業規則に従って行動することが大切です。
会社によっては「1か月前」や「3か月前」などの異なる提出期限が設定されていることがあります。
急な退職は組織に混乱をもたらす可能性があるため、早めの相談が推奨されます。
一般的には「手渡し」が基本ですが、病気や事故など特別な事情がある場合には「郵送」も考慮されます。
手渡しの場合は、就業規則に基づいた期日内に「直属の上司」に適切な時間を選んで、退職の意志を伝えながら退職届を渡します。
会話が他人に聞かれないプライベートな場所、例えば会議室が適しています。
直接の上司以外に退職届を渡すことは避け、感謝の気持ちを表しながら手渡しましょう。
郵送の場合は、体調不良や遠方などで出社が難しい場合、または会社が郵送を許可している場合に限ります。
個人的な理由での郵送は避け、特別な事情がある時だけにしましょう。
郵送する際の注意点
退職届を郵送する場合には、適切なマナーが求められます。
添え状の重要性
郵送では直接の挨拶ができないため、「添え状」を同封し、書面で挨拶を行います。
【添え状に含めるべき内容】
・提出日と退職希望日
・宛先(社名・所属部署・上司の名前)
・自分の所属部署と氏名
・退職届の送付についての説明
正確な基本情報の記載に努め、季節の挨拶と退職届の送付の明記が必要です。
不安な場合は、インターネットで添え状のテンプレートを参考にしてください。
【作成時のポイント】
・手書きでも印刷でも良いが、退職届のフォーマットと一致させる
・添え状も退職届と同じ用紙サイズを使用
・三つ折りにして整える
退職届をA4サイズで書いた場合、添え状もA4サイズで書くのが一般的です。
郵送用の封筒の選び方
退職届を入れる封筒よりも大きいサイズの封筒を用意することが重要です。
【退職届(願)の封筒サイズと郵送用封筒サイズの比較】
●長形4号(90×205 mm)の場合、長形3号(120×235 mm)を使用
●長形3号(120×235 mm)の場合、角形5号(190×240 mm)を使用
添え状を退職届の上に置くことで、封筒が透けて「退職届」の文字が見えにくくなります。
郵送用の封筒には、受取人専用であることを示すために「親展」と赤い文字で記し、四角で囲みます。これは封筒が受取人以外に開封されるのを防ぐためです。
退職届と添え状の封入方法
封筒の裏面にはしっかりとノリを付け、退職届と同じように封筒のフタ部分に「〆マーク」を記入します。
さらに、左下には自分の住所と名前を記入します。
辞表と退職届の違いについて

辞表と退職届は、職を辞する際に必要な文書で、使用する文書は勤務形態や職場との関係によって異なります。
会社員が用いる「退職届」
前述の通り、会社員が雇用関係を終了させる際には退職届を提出します。
この文書は、退職日に労働契約を正式に終了させるために用いられ、通常は人事部門や直接の上司に渡されます。
退職届とよく似た文書に「退職願」がありますが、こちらは退職の意向を伝えるために使われ、主に直属の上司が受け取ります。
これら二つの用語は似ていますが、企業によっては明確な使い分けがされていない場合もあります。どちらを使用するかは上司と相談することが推奨されます。
役員や公務員が使用する「辞表」
辞表は、雇用関係のない者が使用する文書で、辞意を公式に示すために提出されます。
会社の役員や公務員によって使用されることが多く、代表取締役や専務取締役、監査役などが辞表を提出することが一般的です。
役員が実際に労働に従事している場合は、退職時に退職届を求められることもあります。
まとめ
退職届を入れる封筒はコンビニや文房具店ではなく、通販が推奨されます。
退職届封筒の選び方は、白色無地で用紙サイズに合ったものを選ぶことがポイントです。
封筒の作成には油性インクの黒ボールペンや万年筆を使用し、3つの手順を踏むことが重要です。
退職届は通常、直属の上司に対面で渡しますが、特別な事情で郵送も許可される場合があります。
郵送時は大きめの封筒を使用し、退職届が透けないように添え状を上に重ねます。
本記事で退職届の封筒についての購入場所、書き方、渡し方を解説しました。退職届の封筒は意外と見つかりにくいため、早めの準備が推奨されます。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。