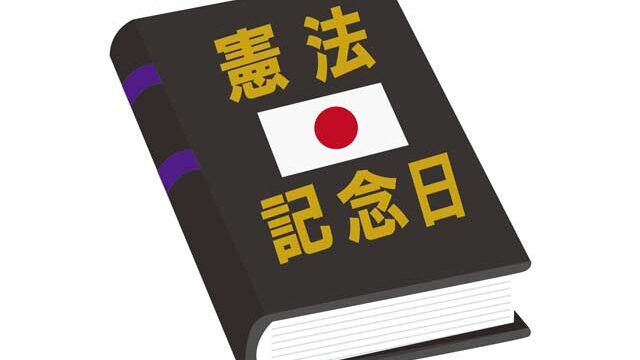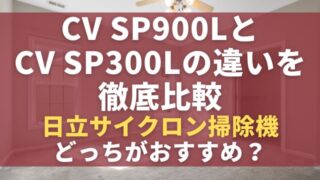「こどもの日」の由来や意義、お祝いに欠かせない食べ物って知ってますか?2024年の祝日一覧も

もうすぐゴールデンウィークがやって来ます。
お出かけの予定を立てられている方も多いのではないでしょうか。
毎年ゴールデンウィークは複数の祝日が集まって形成されますが、今回の記事では5月5日の「子どもの日」の由来や意義、それにまつわる特別な食事についてご紹介します。
子どもの日は、春のゴールデンウィークに位置する重要な休みの一つとして親しまれています。
空を舞う鯉のぼりや、男の子の初節句を祝う家庭で見られる鎧兜や五月人形の飾り付けは、男の子にちなんだ行事として有名ですが、これらには深い意味があります。
もともとは端午の節句(たんごのせっく)と呼ばれ、男の子の誕生や成長をお祝いする行事でした。

昭和時代に入って、この日は国民の休日である「子どもの日」として公式に定められました。
そのため、特に年配の方々の間では「5月5日は端午の節句」という認識が残っているかもしれませんが、60年以上経った今では、性別にかかわらず子供たちの幸せを願う日として広く認識されています。
今回の記事では「子どもの日」の由来や代表的な料理、そして必要不可欠な食べ物について詳しく説明します。
また、2024年の祝日の日付・曜日一覧と、その由来や意義についてもお伝えしていきます。
ぜひ最後までご覧になって、お出かけなどの予定を立てる参考にしてください。
子どもの日の由来とその意義とは?

「子どもの日」は1948年に国民の祝日として設けられました。
もともとは「端午の節句(たんごのせっく)」として知られており、男の子の誕生と成長を祝う目的で行われていました。
この伝統により、子どもの日に鯉のぼりや鎧兜が飾られる習慣がありますが、なぜ男の子中心の行事から全ての子どもを対象とした行事へ変わったのでしょうか。
実は、端午の節句が男の子中心の行事とされたのは、鎌倉時代から江戸時代にかけてで、それ以前の平安や奈良時代には、中国から伝わった災難を避ける意味合いや、日本固有の田植えの神事と結びついた行事として行われていました。
その時代は性別に関係なく行われていたため、端午の節句は元々は男の子だけのものではありませんでした。

さらに、5月5日を国民の休日とする際に「子どもの人格を尊重し、幸福を追求し、母親への感謝を表す」という意図がありました。
そのため、男の子だけでなく女の子も含む全ての子供を対象とする祝日として位置付けられるようになりました。
子どもの日に欠かせない伝統的な食べ物は?

子どもの日には、粽(ちまき)と柏餅(かしわもち)が特に重要な食べ物として挙げられます。
これらは、子どもの日に関連する代表的な料理として知られています。
粽は、中国由来の食べ物であり、端午の節句に関連する重要な人物と深い関係があります。
一方、柏餅は日本で長く伝わる食べ物で、厄除けの効果があるとされています。
粽と柏餅を食べる習慣には地域による差があり、これは中国の文化の影響を受けやすい関西地方と、江戸文化の影響が強い関東地方の違いに基づくとされています。
子どもの日にピッタリな伝統料理とは?
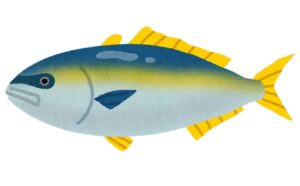
子どもの日を迎えるにあたり、特別な食事を用意しようと考えている方も多いでしょう。
何を作るか迷う方も多いはずです。
子どもの日は、もともと男の子の誕生や成長を祝う端午の節句でした。
そのため、今でもその伝統を引き継ぎ、スズキやブリなどの魚を食べることが推奨されています。

これらの魚が選ばれるのは、成長に応じて名前が変わる「出世魚」だからです。
また、カツオも「勝男」とかけて、端午の節句には欠かせない食材とされています。
そのため、現代の子供の日にも、カツオを含む食事を楽しむことが推奨されています。
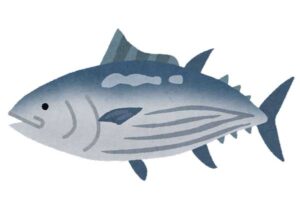
なぜ端午の節句に菖蒲湯に入る?
菖蒲湯(しょうぶゆ)は、子どもたちの健やかな成長と健康を願い、毎年5月5日の端午の節句に行われる特別なお風呂の入り方です。
この風習では、菖蒲の根や葉を湯船に入れて楽しみます。
この伝統は、もともと中国から伝わり、日本で受け継がれてきました。端午の節句は、邪気を避け、健康を願うための行事として中国で行われていたものです。

5月は季節の変わり目で体調を崩しやすいため、菖蒲、健康を守る薬草として活用されていました。
中国では菖蒲を細かく刻んで酒に混ぜたり、家の周りに吊るして使う習慣がありますが、日本ではお風呂に入れて浸かるという独自の方法で今も行われています。
菖蒲湯に入る理由としては、菖蒲の強い香りが邪気を払い、運気を良くする効果があるとされています。
これにより、体を大切にしながら悪い運気を除くという意味が込められているのです。
さらに、この習慣が日本に伝わった当時は武家社会が根付いていたことから、「勝負」「尚武」という言葉遊びを通じて、男の子が力強く成長することを願う思いも表されていました。
鯉のぼりの由来とは?飾る期間はいつからいつまで?
「こどもの日」に飾る鯉のぼりは、もともと「端午の節句」と呼ばれ、男の子の誕生や成長をお祝いする伝統的なイベントでした。
この行事は奈良時代に日本に伝わり、「端」は月の初め、「牛」は幸運な日を意味し、初めは月初の幸運な日に行われていました。
牛と数字の五が結びつき、結果として5月5日を祝う風習が確立しました。
最初は男女関係なく行われていた厄除けも意味していましたが、次第に男の子のための行事へと変わり、江戸時代には鯉のぼりが飾られるようになりました。
こどもの日に鯉のぼりを飾る習慣とその意義にはどのような背景があるのでしょうか。
鯉のぼりの起源と意義
奈良や平安時代には宮中で端午の節句が執り行われていましたが、鎌倉時代には武家の間で菖蒲が流行し、「尚武」や「勝負」との語呂合わせから江戸時代には五節句の一つとして定着しました。
また、将軍家の長男の誕生をお祝いする幟が元となり、庶民も鯉のぼりを立てるようになりました。
鯉のぼりは、鯉が滝を登り竜に変わる中国の故事から、困難を乗り越える強い男性を願う象徴とされています。
鯉のぼりを飾る適切な時期
鯉のぼりを飾る時期には地域による差があり、明確な開始日はありませんが、多くの場合、4月中旬から飾り始めます。晴れた日や吉日に飾るのが良いでしょう。
鯉のぼりをしまう適切な時期
しまう時期も、飾る時期と同様に固定されておらず、通常は5月5日の後に早めにしまうのが一般的です。
しかし、地域によっては5月末や旧暦の6月中旬まで飾っておく習慣もあります。
片付ける際は天候や日にちを考慮するのが適切です。
子供の日のポイントまとめ
子どもの日には、母への感謝の意を表す意味も含まれています。
これはあまり知られていないかもしれません。
子供たちは、母の愛や世話なくしては成長できないため、今年の子供の日には、子供たちだけでなく、母親に対しても感謝の言葉を伝えると良いでしょう。
現代では、住宅環境の変化で鯉のぼりを飾る家庭は減少傾向にありますが、空を自由に泳ぐ鯉のぼりの姿は依然として多くの人を楽しませてくれます。
今年はいくつの鯉のぼりが空を彩るのか、楽しみです。
2024年の国民の祝日一覧
ここからは2024年の国民の祝日と、その由来や意義を簡単にお伝えいたします。
お出かけの予定を立てる際などの参考にしてください。

| 月 | 日付 | 曜日 | 祝日名 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1日 | 月曜日 | 元日 |
| 1月 | 8日 | 月曜日 | 成人の日 |
| 2月 | 11日 | 日曜日 | 建国記念の日 |
| 2月 | 12日 | 月曜日 | 振替休日 |
| 2月 | 23日 | 金曜日 | 天皇誕生日 |
| 3月 | 20日 | 水曜日 | 春分の日 |
| 4月 | 29日 | 月曜日 | 昭和の日 |
| 5月 | 3日 | 金曜日 | 憲法記念日 |
| 5月 | 4日 | 土曜日 | みどりの日 |
| 5月 | 5日 | 日曜日 | 子供の日 |
| 5月 | 6日 | 月曜日 | 振替休日 |
| 7月 | 15日 | 月曜日 | 海の日 |
| 8月 | 11日 | 日曜日 | 山の日 |
| 8月 | 12日 | 月曜日 | 振替休日 |
| 9月 | 16日 | 月曜日 | 敬老の日 |
| 9月 | 22日 | 日曜日 | 秋分の日 |
| 9月 | 23日 | 月曜日 | 振替休日 |
| 10月 | 14日 | 月曜日 | スポーツの日 |
| 11月 | 3日 | 日曜日 | 文化の日 |
| 11月 | 4日 | 月曜日 | 振替休日 |
| 11月 | 23日 | 土曜日 | 勤労感謝の日 |
1月の祝日

●元日(1月1日)
新年の始まりをお祝いする元日は、日本では伝統的に祝日です。
昭和23年に祝日法が施行されるまで、公式には祝日ではありませんでしたが、それ以前から広く休日として認識されていました。
●成人の日(2024年は1月8日、2025年は13日)
「新成人を祝い、自立した大人としての自覚を促す」ための日です。
2000年からハッピーマンデー制度により、1月の第2月曜日に変更されました。
元々は小正月に行われていた元服の儀を起源としています。
2月の祝日

●建国記念の日(2月11日)
「国の建国を記念し、国愛の心を育む」ために、昭和41年に制定されました。
戦後一時期廃止されていた「紀元節」がこの形で復活しました。
●天皇誕生日(2月23日)
天皇の誕生日を祝う日です。
2019年の年号変更に伴い、現在の天皇の誕生日はこの日に設定されています。
3月の祝日

●3月21日(春分の日)
この日は、「自然を愛し、生物を尊重する」思いを胸に、昼と夜の長さがほぼ同じになる春分の日を祝うものです。
春分の日は年によって異なり、通常は3月20日か3月21日に設定されます。
4月の祝日

●4月29日(昭和の日)
昭和時代の終焉とその後の復興を振り返り、将来に向けた希望を考える日としています。元々は昭和天皇の誕生日で、その後みどりの日として祝われていたが、2007年に昭和の日として新しく定められました。
5月の祝日

●5月3日(憲法記念日)
日本国憲法の公布を記念し、昭和22年に施行されたこの日は、「憲法の大切さを再認識し、国の発展を願う」目的で設けられました。
●5月4日(みどりの日)
元々は昭和天皇の誕生日(4月29日)を祝う日としてスタートしましたが、天皇の代替わりと年号の変更に伴い、この日は新たにみどりの日と定義され、その後5月4日に移されました。
自然との調和と感謝を促す日です。
●5月5日(子供の日)
端午の節句として知られ、昭和23年に制定されたこの日は、「子供たちの健やかな成長と母親への感謝」を象徴するための祝日です。
6月の祝日
6月には国民の祝日はありません。
7月の祝日

●7月15日 第3月曜日(海の日)
もともと7月20日に設定されていましたが、現在は7月の第3月曜日に変更されています。「海に感謝し、海洋国家としての繁栄を願う」日として、平成8年に制定されました。
8月の祝日
●8月11日(山の日)
平成26年に制定された山の日は、「山と自然と触れ合うことの大切さを認識し、山から受ける恵みに感謝する」ことを目的としています。
9月の祝日

●9月16日 第3月曜日(敬老の日)
平成14年までは9月15日に設定されていた敬老の日は、平成15年から9月の第3月曜日に変更され、「長年にわたって社会に貢献してきた高齢者を敬い、彼らを祝う」ことを目的としています。
●9月22日(秋分の日)
春分の日と同様、昼と夜の長さが同じになる秋分の日を祝います。
この日はだいたい9月22日か9月23日に設定され、「過去の人々を思い出し、先祖を敬う」日とされています。
10月の祝日

●10月14日(スポーツの日)
1964年の東京オリンピック開幕日である10月10日を記念して、「スポーツを通じて心身の健康を促進する」ことを目的として設けられた日です。
ハッピーマンデー制度により、現在は10月の第2月曜日に祝われます。
2020年1月1日からは、正式にスポーツの日と呼ばれています。
11月の祝日

●11月3日(文化の日)
明治天皇の誕生日であり、日本国憲法の公布日でもあるこの日は、「平和と自由を大切にし、文化の振興を図る」ことを目的としています。
文化の日は、憲法記念日である5月3日の半年後に位置しています。
●11月23日(勤労感謝の日)
かつて新嘗祭(にいなめさい)として知られていたこの日は、アメリカの指示により一時的に禁止された後、「労働を尊重し、生産を祝い、国民同士の感謝を促す」ことを目的として祝日となりました。
12月の祝日
12月には国民の祝日は設けられていません。
まとめ
今回はゴールデンウィーク最後の祝日、「子どもの日」の由来や意義、それにまつわる特別な食事についてお伝えしました。
また、年間の国民の祝日についてもお伝えしました。
今年のゴールデンウィークや、そのほかの祝日のお出かけする際の参考にしていただければ幸いです。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。