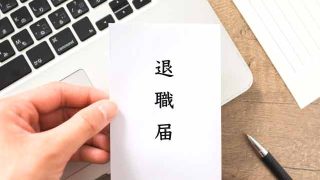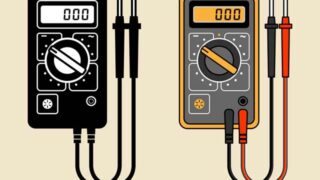7月は夏休みを楽しむ絶好の機会であり、学生から社会人まで様々なイベントや行事が楽しめます。
そこで今回の記事では、7月に開催される17個の主要な行事やイベントを紹介します。
7月を満喫したい方は、下記のイベントリストを参考にして、お出かけの計画を立ててみてください。
7月に注目!イベント&行事のピックアップ17選!
7月はイベント満載の月です。
さまざまなイベントから、興味のあるもの、そうでないものを選んでみましょう。
梅雨明け
梅雨入りはだいたい決まった時期に起こりますが、梅雨明けは年によって変わります。
6月や8月に梅雨明けすることもありますが、通常は7月です。
梅雨明けを迎えると、アウトドアスポーツや高校野球が始まるなど、多くの人にとって待ち遠しい時期が始まります。
海開き

7月といえば、海開きを思い出します。
6月下旬から始まるプール開きに続き、7月には海開きが本格的になります。
「海の日」に合わせて開設される海水浴場も多いですね。
マリンスポーツのファンにとっては、シーズンが始まる大切なイベントです。
山開き

富士山の世界遺産登録後、登山者が急増し、山開きへの関心も高まっています。
山開きの期間は、主に7月に設定されています。
富士山では、山梨県側が7月1日、静岡県側が7月10日に山開きとなることが多いです。
海の日

2024年の海の日は7月17日(月)です。
海の日は7月の第3月曜日に設けられており、ハッピーマンデー制度により月曜日に変更されました。
この日は、海の恩恵に感謝し、海洋国家としての日本の繁栄を願う日です。
海の日を制定しているのは日本のような国は珍しいと、国土交通省が報告しています。
七夕

7月7日は七夕で、五節句の一つとされています。
全国で願い事を書いた短冊を竹に飾る習慣はよく知られています。
七夕のお祭り
「七夕」とも「たなばた」や「しちせき」と呼ばれるこのお祭りは、もともと中国から伝わった行事で、奈良時代に日本に導入されました。この頃、日本に既に伝わっていた「棚機津女」の伝説と結びつき、現在のように広く祝われる形になりました。この行事は日本を含むアジア各地で重要な節句の一つとされています。
笹飾り
七夕では、笹の葉に願い事を書いた短冊や紙製の装飾品を飾るのが一般的です。
7月初旬に飾り付けが始まり、7日の夜までに飾りを外すのが伝統です。
以前は自然に還すためにこれらの飾りを水に流す風習がありましたが、現在は環境保護を考慮し、多くの場合、神社で焼却されます。
焼却が難しい場合は、適切な方法で廃棄されます。
盂蘭盆(うらぼん)
「お盆」とも称されるこの行事は、亡くなった人々や先祖の魂を迎え、その冥福を祈る目的で行われます。
一般的には7月または8月の中旬に設定され、地域によっては13日から16日まで様々な仏教行事が行われます。
【13日】盆迎え火
お盆の初日には、祖霊を迎えるため「盆迎え火」を点火します。
この火は祖霊が迷わずに家を見つけるための道しるべとして、また歓迎の意を表すために用います。
通常、家の入口や門前で素焼きの器である焙烙(ほうろく)におがらを焚きます。
また、盆提灯を玄関に吊るして迎え火として用いる地域もあります。
おがらは13日前にはスーパーや花屋で購入可能です。
【15日】中元
中元は元々、道教の祭日から来た行事で、7月15日を罪を贖う日として設定し、一日中火を炊き続けて神を祭る習慣がありました。
仏教ではこの日を「盂蘭盆会(うらぼんえ)」として祖霊を供養する重要な行事として行います。
これらの行事が結びつき、日本のお盆の一部として定着しました。
中元には感謝の気持ちを込めて贈り物を交換する習慣もあり、これは江戸時代に始まったとされています。
「お中元」は地方によって異なる時期に贈られます。
関東では7月初旬から15日までが主なお中元期間であり、関西では7月15日から8月15日までとなっています。
移住した場合、この時期の違いに注意が必要です。一般的には7月中に送ると良いとされています。
【16日】後の藪入り
藪入りは奉公人が年に二回、実家に帰るための休暇を得る習慣です。
1月16日と7月16日に行われ、7月のものを「後の藪入り」と呼びます。
この習慣は江戸時代に広まり、奉公人は年に2日しか休むことができなかったと言われています。
【16日】盆送り火
お盆の終わりに祖霊を送るために行われる「盆送り火」は、祖霊への感謝と仏の世界への安全な帰路を照らす目的があります。
盆迎え火と同様に、家の玄関や門口で焙烙の上でおがらを燃やします。
盆の明けは地域により15日や16日であり、地域の風習に従って行います。
祇園祭 山鉾巡行(京都)
京都の夏の風物詩である祇園祭は、京都三大祭りの一つとして数えられ、全国的にも知られています。
毎年7月に八坂神社の祭礼として開催され、1か月間にわたって多様な祭事が行われます。
特に7月17日の山鉾巡行は見どころで、京都市内を32基の山鉾が練り歩く姿は圧巻です。
夏祭り

「夏祭り」とは、日本特有の用語で、夏の季節に開催されるさまざまな祭りを指します。
7月に入ると、これらの祭りは本格的に始まり、多くの人々がそれを楽しみにしています。
全国各地で開催されるイベントや祭りが「夏祭り」として知られており、地理的な近さや興味に応じて選ぶことが重要です。
特に関東地方や東京では、100を超えるイベントが簡単に行われ、参加者数も多くなります。
大規模なイベントには毎年数百万人が訪れるため、事前のチェックは欠かせません。
土用の丑の日

2024年の土用の丑の日は7月30日に設定されています。
夏の暑さの中で栄養補給が重要とされ、ウナギを食べる習慣は平賀源内によって広められました。
現在ではウナギが夏バテ防止に直接効果があるとは認められていませんが、この日には多くの人が美味しいウナギを楽しんでいます。
花火大会

7月と8月には、日本全国で花火大会が盛大に開催されます。
デジタル技術を活用した「NAKED 花火アクアリウム」のような花火ショーもあり、地方へ行けない人でも楽しむことができるオプションが増えています。
暑中見舞い
梅雨明けから立秋にかけての期間は、暑中見舞いを送るシーズンです。
これは、親戚やお世話になっている方々への感謝の気持ちを表すもので、贈り物の選択にはセンスが求められます。
適切な贈り物を選ぶことで、暑い時期に思いやりを伝えることができます。
暑気払い(しょきばらい)
昔は、暑い時期に冷たいものを食べたり飲んだりすることが暑気払い(しょきばらい)でしたが、現代では冷たい飲み物や食べ物、時にはお酒を楽しむことも暑気払いとされています。
この風習は飲み会として広く受け入れられ、夏の暑さを乗り切るための方法となっています。
半夏生(はんげしょう)
半夏生(はんげしょう)は夏至から数えて11日目、7月2日頃にあたり、七夕までの5日間です。
この期間は以前は農業において重要な節目であり、田植えの終わりと休息の時期とされていましたが、現代ではその意識は薄れています。
小暑(しょうしょ)

小暑(しょうしょ)は7月7日頃から始まり、この時期には梅雨が明けて暑さが本格化します。
小暑から大暑にかけての約15日間は夏の暑さが徐々に増すため、暑中見舞いの準備を始めるのに適した時期とされています。
大暑の時期(たいしょ)
7月23日頃の大暑(たいしょ)は年間で最も暑い時期です。
この頃は快晴が続き、土用の丑の日にウナギを食べる習慣があります。大暑の時期は夏バテや熱中症対策が特に重要です。
波の日

波の日は7月3日に設けられ、「な(7)み(3)」の語呂合わせが由来です。
マリンスポーツの愛好家が考案し、この日はサーフィンやその他のマリンスポーツのイベントが多く開催され、ファンにとっては見逃せない日です。
夏休み
夏休みは学生にとっては年間で最も長い休暇期間となります。
特に暑さが厳しい地域では、休暇が長くなりがちです。
北海道や東北では夏休みが他地域より短いことがありますが、一般的には7月20日から9月1日まで続きます。
休暇の長さには地域差があり、44日間の地域もあれば、最短で25日間の地域もあります。
マリンスポーツ

マリンスポーツにはサーフィン、ボディボード、ウインドサーフィン、ウォータースキーなど様々な種類があります。
スキューバダイビングのように特定の技術や装備を要するスポーツもあり、ある程度の熟練度が求められます。
7月イベントまとめ
今回の記事では7月に開催されるイベントを紹介しました。
7月は多彩なイベントで賑わいますが、全てを体験するには時間が足りないかもしれません。イベント選びでは居住地やアクセスの便を考慮することが大切です。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。