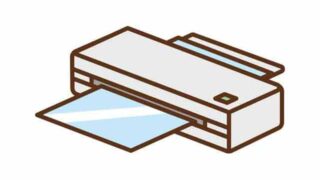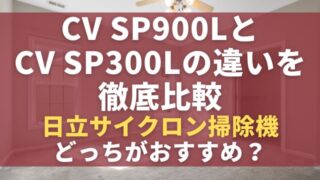【2024年】土用の丑の日の詳細!日付、由来、そしてうなぎを食べる理由
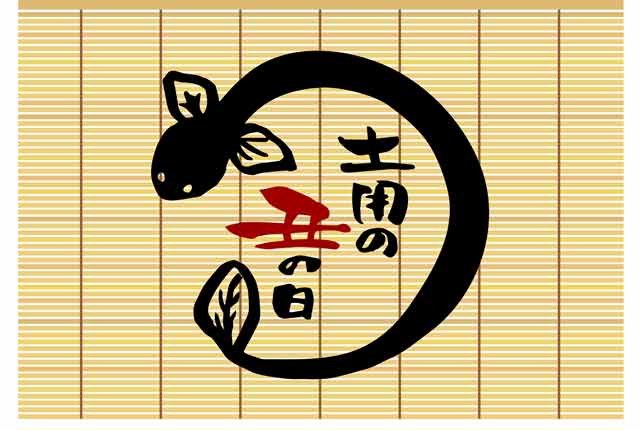
土用の丑の日はうなぎを食べるという伝統がありますが、2024年のその日はいつかご存じですか?
まず、土用とは一体どのような時期を指すのでしょうか。
土曜日だと思っていた方も少なからずいらっしゃるのではないかと思いますが(私です)
実は「土用」は18日間あります。
また、なぜこの日にうなぎを食べるのか、という疑問も浮かんできます。
本記事ではこれらの疑問に答え、土用の丑の日におすすめの食べ物もご紹介します。
2024年の土用の丑の日はいつ?

土用は立秋の前の18日間をさし、この期間中にある「丑の日」を土用の丑の日と呼びます。
2024年には7月24日(水)と8月5日(月)が土用の丑の日に当たります。
以下は、西暦年ごとの土用の期間、丑の日(一の丑)、および二の丑の日付を表形式で整理したものです。夏の土用の丑の日が2回ある年には、1回目を一の丑、2回目を二の丑として表示しています。
| 西暦年 | 夏の土用入り | 夏の土用明け | 丑の日(一の丑) | 二の丑 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 7月19日(金) | 8月6日(火) | 7月24日(水) | 8月5日(月) |
| 2025年 | 7月19日(土) | 8月6日(水) | 7月19日(土) | 8月6日(水) |
| 2026年 | 7月20日(月) | 8月6日(木) | 7月26日(日) | |
| 2027年 | 7月20日(火) | 8月2日(月) | 7月21日(水) | 8月7日(土) |
| 2028年 | 7月19日(水) | 8月6日(日) | 7月27日(木) | |
| 2029年 | 7月19日(木) | 8月6日(月) | 7月22日(日) | 8月3日(金) |
| 2030年 | 7月20日(土) | 8月6日(火) | 7月29日(月) |
※ 夏の土用の丑の日は2回存在することがあります。この場合、1回目を「一の丑」、2回目を「二の丑」と称します。
土用の丑の日の由来について

丑の日とは
「丑」は12干支のひとつで、年間を通して二番目に位置する干支です。
この期間の特定の日が夏の土用の丑の日とされ、うなぎを食べる習慣があります。
土用とは
土用は、「土旺用事」の略で、季節の変わり目に土のエネルギーが活発になる時期を表します。
五行説に基づき、四季に属さない「土」の時期であり、各季節の終わりに18~19日間が土用期間とされています。
土用は立春(2月3日~5日)、立夏(5月4日~6日)、立秋(8月6日~8日)、立冬(11月6日~8日)の直前の18日間で、年に四回、合計72~73日が土用期間となります。
この考え方は、陰陽五行説に基づく古代中国の思想から来ており、自然界や人間生活のあらゆる事象を木、火、土、金、水の五つの要素で説明する学説です。
五行説と季節の要素
古代の五行説では、四季を要素に適用しようとしましたが、季節は四つしか存在しません。
これにより、土の要素に割り当てられる季節が残ります。
そこで、五行説を信じる人々は、土の要素が全季節を通じて影響を及ぼすと考え、各季節の終わりの18日間(または19日間)を「土用」として特定しました。
これにより、「土=季節の変わり目」と定義されることになりました。
・木=春:芽吹きや花が咲く時期です。
・火=夏:強い日差しと暑さが特徴の季節です。
・金=秋:涼しい風が吹き、気温が低下する季節です。
・水=冬:寒さが増し、自然が休む季節です。
・土=各季節の変わり目:計72~73日が土用期間です。
【五行説による自然の要素】
五行説は自然界や人体、宇宙のすべてを五つの基本的な要素で理解しようとする考え方です。ここでは、五行説に関連するさまざまなカテゴリを整理して表形式で示します。
| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十二支 | 寅、卯 | 巳、午 | 丑、辰、未、戌 | 申、酉 | 子、亥 |
| 季節 | 春 | 夏 | 土用 | 秋 | 冬 |
| 方角 | 東 | 南 | 中央 | 西 | 北 |
| 色 | 緑 | 赤 | 黄 | 白 | 黒 |
| 臓器 | 肝臓 | 心臓 | 脾臓 | 肺 | 腎臓 |
| 器官 | 目 | 舌 | 口 | 鼻 | 耳 |
| 時刻 | 朝 | 昼 | 午後 | 夕方 | 夜 |
| 月 | 春季月 | 夏季月 | — | 秋季月 | 冬季月 |
| 声 | 呼び声 | 大声 | 歌声 | 泣き声 | 唸り声 |
| 味 | 酸っぱい | 苦い | 甘い | 辛い | 塩辛い |
| 星 | 木星 | 火星 | 土星 | 金星 | 水星 |
| 五主 | 筋肉 | 血液 | 皮膚 | 皮膚毛 | 骨髄 |
| 家畜 | 羊 | 牛 | 豚 | 鶏 | 犬 |
| 穀物 | 胡麻 | 麦 | 米 | 黍 | 大豆 |
| 元素 | 炭素 | 酸素 | 窒素 | 塩素 | 水素 |
| 五悪 | 風邪 | 熱 | 湿気 | 乾燥 | 寒さ |
| 果実 | 桃 | 杏 | 棗(ナツメ) | 栗 | すもも |
| 守護神 | 青龍 | 朱雀 | 黄龍 | 白虎 | 玄武 |
土は生命を育む力と、終わりを迎えたものを大地に返す役割があります。そのため、季節の変わり目に土の属性を配置することで、季節の移行をスムーズにする効果があるとされています。
四立は各季節の開始を意味し、「立」とは始まりや出発を示します。例えば、夏の土用は立秋の直前の18日間(または19日間)に位置づけられます。
五行の「行」は循環や巡ることを意味し、これらの要素が循環することで自然界のバランスが保たれているとされています。
五行説の相生、相剋、比和の原理
相生
相生(そうじょう)とは、一方が他方の特性を強化する関係を指します。一方が他方をサポートすることでエネルギーが消費され、その過程で強化された五行は弱まることもあります。
例として、火は熱により植物を灰に変え、「土」へと変化させますが、このプロセスで火自体は力を失います。
【相生の関係】
木⇒火(木が摩擦や燃焼によって火を生む)
火⇒土(火が生成した灰が土に戻る)
土⇒金(土中に埋もれた金属)
金⇒水(金から発生する凝結が水を生み出す)
水⇒木(水が木の成長を助ける)
相剋
相剋(そうこく)とは、一方が他方を制し、相性が悪い関係を指します。この関係では、制する側も若干の力を失いますが、制される側は大きく弱められます。
例えば、火は水によって消され、同時に水の一部は蒸発します。
【相剋の関係】
木⇒土(木が土から栄養を吸収して成長)
土⇒水(土が水を吸収し、その流れを阻む)
水⇒火(水が火を消す)
火⇒金(火が金を溶かす)
金⇒木(金が木を切断する)
比和
比和(ひわ)は、同じ性質を持つ五行が互いに力を増幅させる関係を指します。
この相互作用により、同じ属性の要素は強化されますが、バランスが取れていない場合は逆効果を招くこともあります。
一の丑と二の丑の定義
年によっては夏の土用の丑の日が2回訪れることがあります。この場合、最初の日を「一の丑」、次の日を「二の丑」と呼びます。
通常、夏の土用の期間は7月19日から始まることが多いです。一年間で土用の丑の日は平均して6.09日存在し、冬や秋にも土用の丑の日が2回ある場合、後の日を「二の丑」と称します。
土用期間の古い習慣と間日(まび)
古来より、土用期間は土の神である土公神(どくじん)が支配する時期とされています。
この期間中は土に関わる作業、例えば井戸掘りや柱立てなどを避けるべきとする風習があり、これは土を掘る行為が土公神の怒りを招くと考えられていたためです。現在でも、この習慣を守る地域が存在します。
【土用の禁忌事項】
●土を掘る、反転させる
●種を蒔く
●葬式を延期
●井戸掘り
●柱立て
土用期間は年間の5分の1を占めるため、これらの習慣が農作業に支障を来すことがあります。そこで、間日(まび)という特定の日が設けられています。
間日は、土作業ができない人々を助けるために、文殊菩薩(もんじゅぼさつ)が土公神一族を天上の清涼山に集めたことに由来します。
この日は土公神が天に昇るため地上から離れるため、土を掘っても安全とされます。
土用の間日は、季節ごとに特定され、一つの土用期間に3~6日程度存在します。土公神はまた土公様(どこうさま)やかまどの神とも呼ばれ、刃物をかまどに向けることも禁じられています。
土用期間の決定方法
現在、土用の期間は太陽の視黄経が27、117、207、297度に達する日を土用入りと定め、その後の季節の変わり目に配置されます。
つまり、土用明けは新しい季節「立春・立夏・立秋・立冬」の前日となります。
夏の土用の丑の日にうなぎを食べる習慣の背景

夏の土用の丑の日にうなぎを食べる習慣が定着していますが、この風習が広まった背景には複数の説が存在します。
説①「平賀源内の起源説」
この習慣は江戸時代に学者で発明家でもある平賀源内が提案したとされています。
当時、夏にうなぎが売れなかった鰻屋が平賀源内に相談し、彼の提案で「土用の丑の日はうなぎの日」という看板を掲げたところ、大量に売れるようになりました。
これが大ヒットし、他の鰻屋もこれを模倣するようになり、土用の丑の日にうなぎを食べる風習が確立しました。
地方によっては「う」のつく食べ物を食べることが夏バテ防止に効果があるとされ、その結果「う」のつくうなぎが選ばれることになりました。
現在でも夏バテを避けるための食べ物としてうなぎが推奨されていますが、天然うなぎの旬は本来冬にあり、夏は売れ行きが落ちる傾向にあります。それでもうなぎの栄養価の高さは夏にぴったりであると考えられています。
説②「春木屋善兵衛にまつわる伝説」
文政年間に神田泉橋通りにあったうなぎ屋「春木屋」の店主、春木屋善兵衛は、神田和泉橋の藤堂(大名)から大量のうなぎの注文を受けました。
善兵衛は子の日、丑の日、寅の日にそれぞれうなぎを調理し、三日間土蔵で保存してみました。その結果、丑の日に調理したうなぎの風味や色合いが最も良好であったため、これを藤堂に納めました。この出来事が、土用の丑の日にうなぎを食べる習慣の起源とされています。
説③「大田南畝(なんぽ)の影響説」
江戸時代後期の狂歌師、大田南畝(蜀山人とも称される)が神田川のうなぎ屋から依頼を受け、「土用の丑の日にうなぎを食べると病気にならない」という狂歌を作成しました。
この狂歌が人々の間で広く知られるようになり、その結果土用の丑の日にうなぎを食べる習慣が広まったとされる説です。
説④「虚空蔵菩薩と丑の日の結びつき」
虚空蔵菩薩は丑年や寅年の守護本尊とされています。丑年生まれの人々がこの菩薩と結びつけ、うなぎの蒲焼を丑の日に広めたとされる説があります。虚空蔵菩薩は広大な智恵と慈悲を象徴し、知識や記憶力の向上をもたらすと信じられています。このため、虚空蔵を祀る地域や丑年、寅年の人々には特にうなぎを食べる習慣があるとされます。
説⑤「うし(丑)の字の由来説」
「うし(丑)」の文字を墨で書くと、その形が二匹のうなぎに似ているということから、丑の日にうなぎを食べる習慣が生まれたとされる説です。
この視覚的な類似性がうなぎを象徴するものとして捉えられた可能性があります。
土用の丑の日に関連するその他の食べ物

梅干しの利用
梅干しはさっぱりとした味わいで、夏の疲れを癒す効果が期待できます。梅の土用干しは、気候が安定するこの期間に最適で、「土用干し」として知られています。
瓜類の消費
瓜類は水分を豊富に含み、食欲が落ちがちな夏に最適な食品です。代表的な瓜類にはスイカ、きゅうり、かぼちゃ、にがうりなどがあり、これらは夏の旬を迎える時期に美味しくなります。
うどんの摂取
夏場はうどんを含む麺類が消化に優れ、人気を集めています。うどんは「う」で始まる食品の一つとして、特に暑い時期におすすめされています。
ただし、栄養バランスを考慮すると、梅干しと組み合わせて食べるとより健康的です。
「うし(牛)、うま(馬)」について
肉類はエネルギー供給源として知られており、中でも「う」で始まる牛肉や馬肉は、土用の丑の日にうなぎが手に入らない場合の代替食品として選ばれることがあります。
最近では「ステーキ重」などの新しい料理も登場していますが、昔ながらのうなぎの親しみやすさにはまだ及びません。
その他の「う」の付く食べ物
以下は「う」で始まるさまざまな食品をカテゴリ別に整理した一覧表です。
| カテゴリ | 食品名 |
|---|---|
| 魚類 | うるめイワシ、ウグイ、うるか(アユの塩辛)、うまづらはぎ、ウツボ |
| 魚介類 | うに、ウミブドウ |
| 卵類 | ウコッケイの卵、うずらの卵 |
| 肉類 | ウインナー、うさぎ |
| 山菜 | うど |
| 野菜 | うずら豆、うぐいす豆、うぐいす菜、ウコン |
| 果物 | うんしゅうミカン |
| 菓子 | ういろう、うぐいす餅、薄皮まんじゅう |
| 米類 | うるち米、うめおにぎり |
| パン | うぐいすパン |
| 料理 | うの花、うしお汁 |
| 調味料 | うすくち醤油、ウスターソース、うま味調味料 |
| ドリンク | 梅ジュース、ウーロン茶 |
| アルコール | ウイスキー、ウォッカ、梅酒 |
| うなぎ料理 | 蒲焼き、うな重、うなぎパイ、うな丼 |
うなぎは、蒲焼きだけでなく、うな重やうなぎパイ、うな丼なども含まれます。
土用の丑の日に黒い食べ物を食べる伝統
「う」のつく食べ物のほかにも、土用の丑の日には「玄武」を象徴する黒色の食べ物を食べる習慣がありました。
この風習はドジョウやクロダイ、ナスなどの黒い食べ物が好まれたことに由来します。
また、土用蜆(どようしじみ)、土用餅(どようもち)、土用卵(どようたまご)も古くから食べられています。
【黒い食べ物一覧】
以下は、黒い色を持つさまざまな食品をカテゴリ別に整理した一覧表です。
| カテゴリ | 食品名 |
|---|---|
| 魚介類 | ひじき、キャビア、のり(焼き・味付け海苔)、こんぶ、わかめ、黒きくらげ、ドジョウ、クロダイ |
| 野菜 | ごぼう、黒にんにく、黒マカ、ナス |
| 種実類 | 黒ゴマ、黒松の実 |
| 卵類 | 黒卵、ピータン |
| 果物 | 熟したバナナ、ブルーベリー、ぶどう、カシス |
| きのこ類 | しいたけ |
| 豆類 | 黒豆 |
| 米類 | 黒米 |
| パン | 竹炭ベーグル、黒蒸しパン |
| 菓子 | レーズン、プルーン、あんこ、黒蜜、黒飴、コーヒーゼリー、黒ゴマせんべい、チョコレート、黒い恋人、黒糖ドーナツ棒 |
| 調味料 | 黒糖、醤油、黒酢、ソース |
| 飲み物 | ココア、コーヒー、コーラ |
| その他 | こんにゃく、イカスミ、イカスミパスタ、ブラックラーメン、ブラックカレー、黒うどん、ごはんですよ!、のりの佃煮 |
最後に、焦げた食品は健康に良くないことが指摘されているため、過剰な摂取は避けることが推奨されています。
土用餅(どようもち)の伝統
土用餅は、土用の期間に食べられる特別なあんころ餅です。
過去には、暑気あたり予防のためにガガイモの葉を煮出して得た汁でもち米の粉を練り、餅を作りお味噌汁に入れて食べる風習がありました。
江戸時代には、この餅を小豆の餡で包むようになり、あんころ餅として甘味料に変わりました。餅は力を象徴し、小豆には厄除けの意味があるため、これらを食べることで夏の暑さを乗り越え、無病息災を願っていたのです。
土用蜆(どようしじみ)の特徴
しじみには寒しじみと土用しじみの二つの旬があり、土用しじみは夏に旬を迎えます。
特に肝臓の健康を支え、夏の疲れを解消するのに役立つとされています。
ヤマトシジミなどのしじみは夏に栄養価が高まり、味も良くなるため、古くから土用の期間に好んで食されています。
土用卵について
土用卵とは、土用の期間にニワトリが産む有精卵のことを指します。
昔からこれらの卵は栄養価の高さから滋養強壮食とされ、うなぎと同様に精をつける食品として珍重されてきました。
卵に含まれる栄養は細胞の成長や神経系の発達に必要で、現代でもその完全栄養食品としての価値が認められています。
土用の伝統的な風習
土用の虫干し
土用の虫干しは、梅雨時に湿気がこもった衣類や物品を風通しの良い場所で陰干しする行為です。
夏の土用はしばしば梅雨明けと重なるため、この時期は湿気を除去するのに最適なタイミングとされ、書物や布団、衣類などが干されていました。
丑湯の伝統
丑湯は、土用の丑の日に特定の薬草、例えばドクダミや桃の葉を用いた入浴法です。
この習慣は夏バテ防止や疲労回復を促し、古くは桃の葉を使った桃湯が丑湯として知られていました。現代でも、薬草を使った風呂は健康増進や美肌効果が期待されています。
土用の丑の日の総合ガイド
土用の丑の日に関連する食習慣や風習には様々な起源がありますが、夏の暑さに負けないためには、うなぎを含む栄養価の高い食品を摂取することが推奨されています。
もし夏バテが心配なら、上記の食品を取り入れて、元気に夏を乗り切りましょう。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。