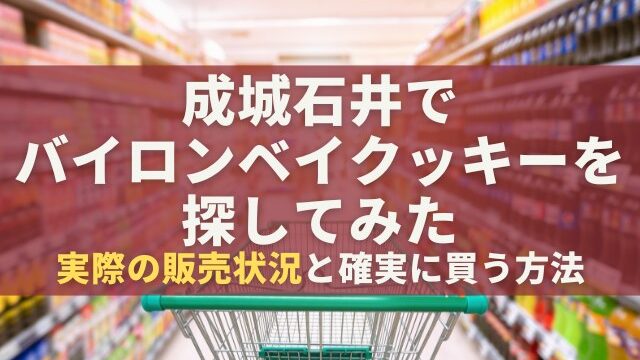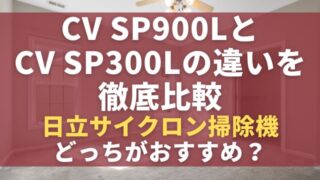将棋の八大タイトル戦における賞金構造、階層、および永世称号の詳細解説

現代将棋界では、藤井聡太氏が史上最年少で名人位を獲得し、八冠全冠制覇という類まれな成果を達成しています。
羽生善治氏は7つのタイトルで永世称号を獲得し、2018年には国民栄誉賞を受賞しました。
本解説では、将棋の各タイトル戦の階層、賞金額、主催者、永世称号の基準について詳しく説明します。
プロ棋界について

プロ棋界では、現役および引退した棋士を含めて230名以上の棋士が活動しています。
現在、棋士の大半は男性ですが、女性も棋士になることが可能です。特に、女性専用の「女流棋士」というカテゴリーが設けられており、詳細は後ほど説明します。
棋士になるためには、奨励会という棋士育成機関への入会が必要です。奨励会への入会資格は一定の年齢制限が設けられており、棋士の推薦を受けた者のみが受験できます。
奨励会は6級から始まり、三段に至るまでの段階があります。
プレイヤーは6級から順に昇段し、1級、初段、二段を経て三段に到達します。三段リーグは年2回開催され、このリーグで上位2名が四段に昇段し、正式な棋士となります。
棋士として認定された後は、様々な棋戦に参加する機会が得られます。これには8つのタイトル戦と7つの公式棋戦が含まれています。
将棋界の重要な八大タイトル戦の概要

プロ棋士が競う重要な棋戦には、八大タイトル戦のほかに、朝日杯、NHK杯などの公式戦があります。
特に重要視されている八大タイトル戦は、竜王(りゅうおう)、名人(めいじん)、王位(おうい)、王座(おうざ)、棋王(きおう)、叡王(えいおう)、王将(おうしょう)、棋聖の8つのタイトルで構成されています。
これらのタイトル戦は、現在のタイトル保持者と挑戦者が五番勝負や七番勝負で対戦し、勝者がタイトルを獲得します。タイトル保持者は、名前の後にタイトルを添え、「〇〇竜王」などと称されることがあります。
竜王戦と名人戦では、年に1回のランキングに基づいた昇降級が行われます。
八大タイトル戦の序列と基準
八大タイトル戦の序列は、賞金と対局料の総額を基準に定められています。
この序列は以下の順になっています。
- 竜王(りゅうおう)
- 名人(めいじん)
- 王位(おうい)
- 王座(おうざ)
- 棋王(きおう)
- 叡王(えいおう)
- 王将(おうしょう)
- 棋聖(きせい)
竜王はその歴史と格式の深さから、名人タイトルと並んで特別な評価を受けています。
名人戦は他のタイトルに比べて通常、重要度が高く見られ、その地位は最も高いとされることがあります。
竜王(りゅうおう)
設立年度:1988年
開催期間:10月から12月
賞金:4320万円
対戦形式:7番勝負(4勝先取)
主催者:読売新聞社
竜王戦
竜王戦には全棋士、女流棋士4名、奨励会員1名、アマチュア4名が参加します。
参加者は1組から6組までのグループに分けられ、トーナメントを通じて各グループから上位11名が挑戦者決定トーナメントに進みます。
挑戦者と竜王は通常、10月から12月にかけて7番勝負を行います。

名人(めいじん)
設立年度:1935年
開催期間:4月から6月
賞金:2000万円
対戦形式:7番勝負(4勝先取)
主催者:朝日新聞社、毎日新聞社
名人戦
名人戦では、フリークラスを除く全棋士がA級からC級2組までの5つのクラスに分けられ、リーグ戦を行います。A級で首位が同点の場合は、同点棋士全員でプレーオフを実施します。名人とA級の勝者は通常、4月から7月にかけて7番勝負をします。
王位(おうい)
設立年度:1960年
開催期間:7月から9月
賞金:1000万円
対戦形式:7番勝負(4勝先取)
主催者:ブロック紙3社連合(北海道新聞社、中日新聞、西日本新聞)
王位戦
王位戦には全棋士と女流棋士2名が参加し、予選はトーナメント形式で行われます。
勝ち上がり者とシードされた4名が紅白2ブロックでリーグ戦を行い、リーグ戦の優勝者が挑戦者として選ばれ、通常7月から9月にかけて7番勝負を行います。
王座(おうざ)
設立年度:1983年
開催期間:9月から10月
賞金:800万円
対戦形式:5番勝負(3勝先取)
主催者:日本経済新聞社
王座戦
王座戦には全棋士と女流棋士4名が参加します。一次予選と二次予選はトーナメント形式で行われ、二次予選を通過した棋士とシード棋士16名で挑戦者決定トーナメントが行われます。王座と挑戦者は通常、9月から10月にかけて5番勝負を行います。
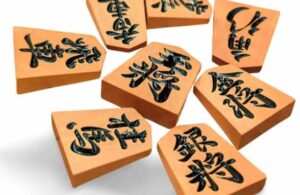
棋王(きおう)
設立年度:1975年
開催期間:2月から3月
賞金:600万円
対戦形式:5番勝負(3勝先取)
主催者:共同通信社
棋王戦
棋王戦には全棋士、女流棋士、アマ名人が参加します。予選はトーナメント形式で、通過者とシード棋士が本戦トーナメントで競います。
本戦トーナメントはベスト4以上が2敗失格制で、敗者復活戦があります。
挑戦者決定戦は変則2番勝負で、勝者組の優勝者は1勝で挑戦権を得る一方、敗者復活戦の優勝者は2連勝が必要です。棋王と優勝者は通常、2月から3月にかけて5番勝負を行います。
叡王(えいおう)
設立年度:2017年
開催期間:4月から6月
賞金:300万円から600万円
対戦形式:5番勝負(3勝先取)
主催者:不二家
叡王戦は2015年に一般棋戦として初めて開催され、2017年からは正式なタイトル戦として認定されました。これは八大タイトル戦の中でも最新のタイトルです。
叡王戦
叡王戦には全棋士、女流棋士1名、アマチュア1名が参加し、段位別予選と本戦トーナメントで構成されます。本戦トーナメントは段位別予選を勝ち抜いた棋士とシード棋士24名が行い、最終的に2名が挑戦者決定三番勝負を行い、その勝者が七番勝負の挑戦者となります。
王将(おうしょう)
タイトル戦開始年:1951年
開催期間:1月から3月
賞金:300万円
対戦形式:7番勝負(4勝先取)
主催者:スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社
王将戦
王将戦には全棋士が参加し、一次予選と二次予選をトーナメント形式で行います。
その後、勝ち上がった棋士とシード棋士4人がリーグ戦に進み、リーグ戦で同率首位の棋士が複数出た場合、通常は上位2名がプレーオフを行います。
王将とリーグ優勝者は、例年1月から3月にかけて7番勝負を行います。
棋聖(きせい)
タイトル戦開始年:1962年
開催期間:6月から7月
賞金:300万円
対戦形式:5番勝負(3勝先取)
主催者:産経新聞社
棋聖戦
棋聖戦には全棋士と女流棋士2名が参加します。一次予選と二次予選をトーナメント形式で行い、その勝ち上がり者とシード棋士16名で決勝トーナメントを行います。
優勝者と棋聖は、通常6月から8月にかけて5番勝負を行います。
特別扱いされる竜王と名人

将棋界において、竜王と名人のタイトルは他の8大タイトルと比べて特別な扱いを受けています。
これらのタイトルは、他のタイトルを持っていても「竜王・名人」や「竜王」、「名人」として呼ばれます。
昇段においては特権が与えられ、竜王は1期で八段、2期で九段に、名人は1期で直接九段に昇段できます。
他のタイトルでは、1期で七段、2期で八段、3期で九段と昇段するのが一般的です。
また、日本将棋連盟が発行するアマチュアの段位認定では、会長と共に竜王と名人のタイトル保持者が署名を行うのが慣例です。
将棋界に「十段」というタイトルは存在するか?
囲碁界に「十段」というタイトルが存在しますが、将棋界にも同様のタイトルがあったのでしょうか?
実は、1962年から1987年まで、将棋にもありました。
この十段戦の主催は読売新聞社でしたが、1988年に十段戦は終了し、新たに竜王戦がスタートしました。
この変更の際、読売新聞社は竜王戦の賞金を名人戦を超える額に設定し、竜王戦を名人戦以上の序列に位置付けるよう要望しました。
その結果、竜王戦が最上位の序列とされました。
八大タイトル戦と永世称号
永世称号は、タイトルを保持した上で、さだめられた条件を満たした棋士が、引退後にその称号を名乗れる制度です。
以下に各タイトルごとの永世称号の名称、獲得条件、及び永世称号資格保持者の情報を示します。
| タイトル名 | 永世称号名 | 獲得条件 | 永世称号資格保持者 |
|---|---|---|---|
| 竜王 | 永世竜王 | 連続5期または通算7期 | 渡辺明、羽生善治 |
| 名人 | 永世名人 | 通算5期 | 木村義雄、大山康晴、中原誠、谷川浩司、 森内俊之、羽生善治 |
| 王位 | 永世王位 | 連続5期または通算10期 | 大山康晴、中原誠、羽生善治 |
| 王座 | 名誉王座 | 連続5期または通算10期 | 中原誠、羽生善治 |
| 棋王 | 永世棋王 | 連続5期 | 渡辺明、羽生善治 |
| 叡王 | 規定なし | - | - |
| 王将 | 永世王将 | 通算10期 | 大山康晴、羽生善治 |
| 棋聖 | 永世棋聖 | 通算5期 | 大山康晴、中原誠、米長邦雄、羽生善治、 佐藤康光 |
将棋界の歴史の中で印象的な成就を果たした棋士と達成日
将棋界には現在、主要な8つのタイトルが存在しているのは前述の通りです。
藤井聡太八冠はこれらすべてのタイトルを獲得し、全タイトル独占という偉業を成し遂げました。これは、羽生善治九段が1996年に七冠を達成して以来の快挙です。藤井八冠はプロデビューからわずか7年でこの地位に立ちました。
八冠
●藤井聡太(名人、棋王、王将、竜王、王位、叡王、棋聖、王座)
達成日:2023年10月11日(21歳2カ月)
七冠
●羽生善治(竜王、名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖)
達成日:1996年2月14日(25歳4カ月)
羽生善治は2017年まで、叡王を除く既存の7つのタイトルを全て制覇し、「永世七冠」の称号を獲得しました。
六冠
●藤井聡太(棋王、王将、竜王、王位、叡王、棋聖)
達成日:2023年3月19日(20歳8カ月)
五冠
●大山康晴(名人、十段、王将、王位、棋聖)=故人
達成日:1963年2月2日(39歳10カ月)
四冠
●大山康晴(王将、九段、名人、王位)=故人
達成日:1960年9月20日(37歳6カ月)
三冠
●升田幸三(王将、九段、名人)=故人
達成日:1957年7月11日(39歳3カ月)
ここでは将棋界の各タイトルを保持し、それぞれの棋士がいつ何のタイトルを獲得したかを示しました。将棋界の歴史の中で特に印象的な成就を果たした棋士たちの記録が詳細に伝えられます。
まとめ
特に竜王と名人のタイトルは、他のタイトルよりも格式が高いとされ、これらは棋士の昇段条件などで特別な位置を占めています。
1988年に十段戦が竜王戦へと移行し、竜王戦が序列の最上位に設定されました。
一方、名人戦は、その伝統と歴史からかつては最上位に位置していました。
八大タイトルを獲得することは、棋士の段位に大きな影響を与えます。
また、「永世」の称号は、将棋界の歴史に残る快挙を果たした棋士に与えられ、引退後もその称号を名乗ることが許されるため、将棋界で彼らの地位を不動のものとします。
この先また、どんな棋士が出てくるのか楽しみですね。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。