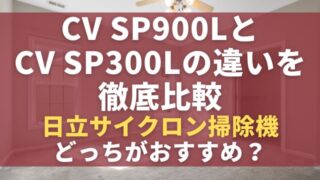雛人形の右大臣の顔が赤い理由は?左大臣との地位の違いについても

雛人形の段飾りには、さまざまな役職を持つお人形が並びます。
特に、「右大臣」と「左大臣」は注目されがちです。右大臣の顔が赤いのは何故か、そして彼らの地位に関する興味深い疑問について解説します。
なぜ右大臣の顔は赤いのか?

右大臣の顔が赤いのは、高齢を象徴しているか、あるいはお酒を好むことを暗示している可能性がありますが、これについては確定的な理由は明らかにされていません。
これらの人形は「右近衛少将」と「左近衛中将」とも正式に呼ばれ、主に天皇や皇后の護衛を務める随身としての役割を持っています。
雛人形の飾りは、天皇と皇后の結婚式を象徴しており、右大臣と左大臣はその式がスムーズに行われるよう見守る役目を担っています。
左大臣と右大臣、どちらが上位に立つのか?

地位に関して言えば、左大臣が上位であり、通常は年長者です。
しかし、興味深い点として、雛祭りの歌の「赤い顔の右大臣」というフレーズは実際には左大臣を指しています。
雛祭りの歌の誤り
よく知られている雛祭りの歌における「赤いお顔の右大臣」という表現は、実際には誤りで、赤い顔を持つのは左大臣です。これはお内裏様である男雛の視点から見ると理解しやすく、古来の「左上位」の考え方により、左大臣が右大臣より地位が高いことを示しています。
「天子南面す」
雛人形は天皇と皇后の結婚の儀を表しており、天皇は「天子南面す」の規則に従って常に南を向いて座ります。これにより、東は左手に位置し、日の出を迎える東が西より優れているとされています。このため、左大臣が知恵を、右大臣が力を象徴しています。
京雛と関東雛の配置の違いについて

日本では「左上位」が伝統的な考え方とされていますが、雛人形の配置には時代や地域による変化が見られます。
特に、「関東雛」と「京雛」の配置は異なります。
関東雛では、男雛が向かって左側、女雛が右側に置かれるのが一般的です。
これに対し、京雛では女雛が左、男雛が右に配置され、従来の慣習が守られています。
この配置の差は、大正時代に西洋文化の影響を受けた結果とされます。
西洋では「右上位」が通常であるため、関東地方の雛人形の配置もこれに倣って左上位から右上位へと変わったと考えられています。
京雛と関東雛は、人形の表情や持ち物、装飾の詳細にも違いが見られますが、男雛と女雛の配置を除いては、他の役職の配置には共通点が多いです。
右大臣と左大臣の名称は徐々に意味があいまいになっていますが、これらの人形は伝統的な序列に沿って配置されることが多く、赤い顔を持つ年配の大臣が上位に位置することは一般的です。
結論
雛祭りの歌に出てくる「赤いお顔の右大臣」が実際には左大臣であり、その赤い顔が年配者を象徴していることは確かです。
年長の大臣が高い地位にあるという事実に変わりはありませんので、これらの伝統や背景に興味がある方は、さらに情報を探求することがお勧めされます。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。